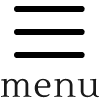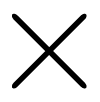コラム
マンションリフォーム顛末記 その②
自宅マンションのリフォーム工事が始まって3週間程経過。
一時は住みながらのリフォームを後悔したのだが、
工事の進捗を毎日確認できるのと、工事内容の修正打合せ等も都度できるので、
結果よかったかも(現場監督はイヤだったかもしれないが💦)。
「リフォーム顛末記」2回目は佳境に達したリフォーム現場からお伝えしたい。
酷暑の中、エアコンを使えない日が2週間ほど続き、
扇風機を回しても毎夜汗びっしょりで、
「まるでおうちサウナだよね」などと妻と冗談を言い合っていたが、
さすがにこの夏の暑さは危険域に達したのではと思うほどで、
すでに相当な夏バテ感でどんよりなのである💦
しかし、よく熱中症にもならず頑張れたものだ。
毎日、キャンプ飯よろしく
「工事現場」のなかでキャンプ用の組み立てテーブルで朝食と夕食をとっていると
これはこれでなかなか体験できない日常なので、面白くもあった。
解体撤去された部屋内に、新しい床が貼られ、新しい壁紙が貼られ、
新しいバスルームや洗面台、キッチンが運び込まれ、
あれよあれよという間に新しい装いに姿を変えていく我が家。
あぁ、これがリフォームなのかぁ、などと感慨深い(ようやく実感がわいてきた:遅っ!)
間取りも少し変えたので、
LDKからの眺望が予想通りリフォーム前より広がり、妻もご満悦。
山、空、海、いずれもキッチンや居室から外の視野に広がるので、
リフォームのコンセプトであった「海と風」を感じる家はほぼ実現できそうだ。
お盆過ぎからは、最後に残った和室の工事に入る。
しかし、我が家のリフォームもあと2週間ほどで終わるのか、
なーんて思うと、なんだかちょっと寂しいのである。
色々大変だったけど、「リフォーム現在進行中」を体験できるって、
けっこう楽しいものなのかもしれない。
もちろんリフォーム完了後の我が家はもっと楽しみなのだが。。
次回「リフォーム顛末記」3回目は、今回のリフォーム内容の詳細と
良かった(成功した、かも)点、イマイチ(失敗した、かも)な点を取りまとめてお伝えします。
マンションリフォーム顛末記 その①
自宅マンションのリフォーム工事が始まって1週間程経過。
住みながらのリフォームを選択したので、それなりに大変だ。
このコラムでは、数回にわたって「リフォーム顛末記」を掲載したいと思う。
中古マンションを買ってリフォームしようかな、
なーんて方には参考にしていただけるところもあるかも(ないかも)。
そもそもリフォームを思い立った経緯から。
息子、娘も巣立って早10年超。その間夫婦仲良く(と言っておく😊)暮らしていたが
新築購入以来28年、トイレのリフォーム以外は手つかずのまま。
一時娘がウサギを飼っていたこともあって、室内はボロボロ💦
ようやく来春娘の結婚も決まり、なんだか一息ついた感もあって、
それと夫婦お互い60歳代半ばも過ぎたこともあり、
「あと何年住めるかわからんけど、前から何とかしたかったキッチン周りを中心に
リフォームしたい!!」と妻が言い出したのがきっかけ。
私は平日仕事で、家にいるのは「晩酌しながら飯食って音楽聴いて寝るとき」だけで、
休日はクルマにSUPになんだかんだと、ほとんど家にいないので
リフォームの「リ」の字も頭になかった。
ということで、嫁に先導されリフォームを決めた、というわけだ。
そこからはバタバタ計画が進む。まずリフォーム会社決め。
仕事柄工務店のクライアントもあり、リフォームをやっているところもあるのだが、
なんかあったときに強く言えないのもイヤだから(気が弱いので)、
ネット検索して良さげな近場のリフォーム会社に白羽の矢を立てた。
そして夫婦で、あーでもないこうでもないこれがしたいあれがしたい、
とお互いの主張をぶつけあい、合意に達したリフォームプランが以下の通り。
◎リフォームのコンセプトは「海と風」。
自宅の窓から、博多湾、今津湾が見渡せるので、その立地をいかして
可能な限り室内と海とのつながりを作ること。
まずは、全室壁紙、床の張替えをして、さらに間取りや仕切りを再構築する。
◎リフォーム計画の概要
・各居室から海の眺望をより拡大すること
・キッチンからテレビが見られるように、
また海を含む眺望も確保したい ← 妻のたっての希望!
・各居室の風の通り道を増やすこと(山風、海風が通り抜けます)
リフォーム会社との数回の打ち合わせを済ませ
妻が特にこだわったキッチンや水回りのショールームを
数週間かけて複数か所見学し、最新設備機器をチェック。
また、壁紙や床材、カーペット、照明等々
仕様や素材、色味などを吟味し、見積りも何回か取り直し、
ようやく6月末に工事内容が決まり発注!
工事の工程も決まったところでマンションの管理組合にリフォーム申請をし、
7月16日(火)工事着工の運びに。
(しかしここまで至るに、まあまあ疲れた。。)
工事の前段階の準備は、けっこうな力仕事。
着工の前に、最後に工事にとりかかる和室(6畳)に
とりあえず各室(4LDK)の家財道具他一切のモノを運び入れるように、
とのリフォーム会社からのお達し。
7月15日の海の日を含む3連休は、まるで引っ越しをするのではと思うほど
本棚やタンスを動かしたり、段ボールにモノを詰め込んだりで
腰は痛くなるは、夫婦げんかは始まるわで、疲労困憊。
しかし、オーディオやレコード・CD、本や雑誌など
私の趣味部屋を埋め尽くすこれらの雑多なモノのなんと重たいこと!
妻に嫌味を言われ、自業自得とはいえ恨めしくも思いながら、
汗だらだらでリフォーム会社の指示通りの
作業を完了したのは工事着手の前日の20時頃。
(翌日以降しばらく、体中が悲鳴を上げていたのは言うまでもない)
工事開始の最初の1週間弱は寝室、趣味部屋、
トイレ、バスルーム、洗面所の工事の日程なので、自宅に居場所がなく、
団地内のマンションのゲストルームを身の回りの荷物を持って泊まり歩くという
流浪の日々。一時的にクルマに荷物を詰め込んだり、出したりでこれはこれで疲れる。
そのうちに何がどこにあるのか分からなくなり、
ハンカチや靴下などを探し回ってイライラは募るばかり。
(お察しの通りここでも夫婦げんかが勃発する)
先週20日(土)にようやく最初の工程の工事が終了したので、
最低限自宅で暮らせるようになり、工事途中だが、自宅へ戻ってこれた。
やれやれ。やっぱ自宅はいいね~と思う間もなく、
寝室と趣味部屋、トイレ、洗面所、バスルーム以外は
外履きのサンダルを履いて「工事現場」を歩きまわるという、
落ち着かない暮らしが続くのである。。
リフォーム工事完了まであと3週間ほどかかるが、完成が楽しみなのはもちろんだが、
妻が待ち望んでいる新しいキッチンが設置されるまで(旧キッチンは撤去済み)、卓上コンロを使いながらまるでキャンプのような不便さ(?!)をこなせる(耐える)か、ここは踏ん張りどころ。
我が家の唯一のエアコンはリビングにあって、室内の現状は床を剥いでコンクリむき出し、しかも工具や建材が置いてあって埃っぽいので、しばらく使用不可なのだ。
扇風機を回しているが、夜でも30度超えの連日の熱帯夜との戦いも
しばらく続きそうだ💦(つづく)
買い替えで実現! 住まいのダウンサイジングでゆ~ったり暮らそう。
福岡都市圏の中古マンションが高騰していますが、所有者の中には、今のうちに売却して住み替えようかな、と思っている方もいらっしゃるのでは?でも次に買い替えを検討している中古マンションも、当然高くなっていますし、同じエリアで買い替えても資産効果はあまり期待できないかもしれませんよね。それなら、住み替えはやめておこうかな、と思い悩んでいる方も多いのではと思います。
しかし、中央区の中古マンション高騰エリアに4LDKの広いマンションを所有していて、子供が独立してライフスタイルも購入当時とは変わり、もっとのんびり暮らしたいな~、なんていう方は、住み替えを検討してみる価値はありそうです。
例えば、西区など物件価格が比較的安いエリアの、3LDKの手頃なマンションに住み替えるプランなどはいかがでしょうか。
住み替えの目的としては、住居スペースと住居費(イニシャル+ランニング)をダウンサイジングして、いまの仕事中心の生活から「趣味や休日を楽しむゆとりのある暮らし」を目指そうというものです。
そこで、レインズ※1のデータを参考に、買い替えのシミュレーションを行ってみました。
◎自宅売却物件 福岡市中央区某所 4LDK 90㎡ 5,000万円 2004年新築購入 築20年
※ローン残債:1,500万円
◎買い替え購入物件 福岡市西区某所 3LDK70㎡ 3,000万円 1996年新築 築28年
売り買いのお金の動きをざっくり計算してみます。
◎売却に係る費用
・売却額=5,000万円
・売却に係る費用=売却価格の凡そ5%(として)=250万円(仲介手数料含む)
・売却後の手残り額=5,000万円-ローン完済1,500万円-250万円=3,250万円
◎購入に係る費用
・購入費=3,000万円 ※住宅ローン利用なし
・購入に係る費用=購入費用の5%(として)=150万円(仲介手数料含む)
◎買い替え後の収支=3,750万円-3,000万円-150万円=600万円
600万円の手残りがありますので、引っ越し費用、リフォーム費用、家具・家電買い替え費用等に充てることも可能です。この収支でしたら、実行してみる価値はありそうですね。
しかも、今まで支払っていた住宅ローンがなくなり、毎月の管理費や修繕積立金、駐車場代、そして年4回の固定資産税もおそらく安くなることから、余裕の暮らしが実現できるかもしれません。
海が好きなら「リゾート感のある海辺の中古マンション」に住み替えてみる、というのもなんだかワクワクしますよね。
さあ、この住まいのダウンサイジング計画、いかがでしょうか?
※1指定流通機構=「レインズ」
レインズ(Real Estate Information Network System)=指定流通機構は、不動産物件の流通を素早く、円滑にするため、数多くの不動産業者が加盟してできた不動産情報ネットワークを運営する公益法人で、この不動産物件情報交換のためのコンピュータ・ネットワーク・システムのことをレインズといいます。
数多くの不動産業者がネットワークされているため、豊富な物件情報の中から買い主は買いたい物件を売り主は物件の売却先をスピーディーに安心して見つけられるようになります。(西日本レインズ公式サイトより引用)
※2 3,000万円特別控除
居住用財産の売却益は「譲渡所得」となり課税(約20~40%)されますが、一定要件を満たせば3,000万円を控除できる特例(3,000万円特別控除)があります。
譲渡所得は居住用財産の売却によって得た利益となるので、以下のように計算します。
譲渡所得=売却価格 - 取得費 - 譲渡費用(※売却価格の5%相当)
計算結果がマイナスであれば譲渡所得が発生しておらず、計算結果がプラスであっても
3,000万円以下のときは特例によって譲渡所得が非課税になります。
例:(5,000万円 - 3,000万円 – 250万円)= 1,750万円
1,750万円- 3,000万円(特別控除) = -1,250万円
→ マイナスなので非課税 ※ただし、翌年、確定申告が必要になります。
現在の年収で無理せずにいくらのマンションを買えるか?
賃金の上昇もあまり期待できない中、物価はじわじわ上がり、金利も上昇しつつある中、
このタイミングでマンションを買おうかどうか迷っている方も多いのではないでしょうか。
そこで福岡の宅建士エージェントがマンション購入のシミュレーション例をご紹介します(あくまでも個人的な見解です)。
◎はじめに
一番大事なのは、物件探しから始めないことです。買えない物件を見ても、気持ちが凹んでいくだけです。夢がない話ですが、まずは年収から現実的にどれくらいの物件なら買えるかを見ていきます。そもそもですが、年収に見合わない家の購入は家計に対してのリスクが大きすぎ、将来確実に年収増や所得が見込まれる方以外は、現在の年収ベースに住宅取得を考えましょう。
◎現在の年収ならいくらまで住宅ローンが組める?
厚生労働省のデータから集計した福岡県の30歳代(35歳~39歳)平均年収は以下のようになっています。
男性 月収31万円 ボーナス98.6万円 年収471万円
女性 月収23.5万円 ボーナス59万円 年収341万円
住宅購入予算の目安になるのが「年収倍率」です。年収倍率とは、購入予定の住宅価格が世帯年収の何倍であるかを表す数値のことです。金融機関が住宅ローンの審査を行い、融資可能額を決めるときも年収倍率を参考にします。
ちなみに、住宅金融支援機構の「2022年度フラット35利用者調査」によれば、2022年度にフラット35を利用してマンションを購入した人の年収倍率は、新築で全国平均7.2倍、中古で5.9倍の実績でした。しかし、無理のない返済額を考えると5~6倍が適正というデータもあります。
ではこの年収倍率(中古6倍~新築7倍)を目安に購入可能額を見ていきます。
◎いくらのマンションなら買っていい?
ここでは、家計収入のうち、ご主人(男性)の収入のみをベースに計算していきます。これは配偶者(女性)の収入は将来的に出産や子育てなどでご主人より不確実な場合があるからです。ある意味リスクを最小化したケースと思ってください。リスクが軽減されればその分貯蓄等に回せて安心ですしね。
仮に ご主人が38歳 年収480万円 と仮定して年収倍率※(全国平均)を適用すると
新築マンション 年収の7倍=3,360万円
中古マンション 年収の6倍=2,880万円
マンションを購入するなら上記の金額を目安に探すのが現実的ということになります。頭金の準備や親御さんの援助があれば算入してもいいでしょう。
また、年収に占める住宅ローンの年間返済額の割合を「返済負担額」と言い、20~25%目安が無理のない年間の返済額と言われています。
この場合、480万円×20~25%=96万~120万円が年間の無理のない返済額となります。月額で計算すると8万円~10万円の返済額ということになります。
※融資可能額の査定は金融機関によって異なります。
マンション購入時に諸経費として購入価格の10%前後必要となり、購入後は、毎月のローンの支払いのほかに、管理費・修繕積立金、駐車場代などが毎月かかってきますし、年4回の固定資産税などの税金の負担もありますので、余裕をもった資金計画を立てることが肝要です。
◎まとめ
いかがでしたでしょうか?このところ福岡都市圏では新築マンションが高騰しているので、中古マンションを購入し、リフォーム(リノベーション)してお気に入りのマンションライフを手に入れたという方も増えているようです。余談ですが、リフォーム会社の方のお話を聞いたら、最近は閑散期がなく1年中忙しいとおっしゃってました。
ちょっと古いマンションはまだお手頃な物件もあるようですので、壁紙や床・天井を張り替えて、キッチンやお風呂、洗面台、トイレなどの水回りの住宅設備を最新の機器に替えるだけでも、見違えるようにリフレッシュしますよ。
まずは無理のない資金計画を立てて、マンション・ハンティングに出かけませんか?
「福岡の宅建士エージェント」がお手伝いさせていただきます。
福岡のマンションはいつまで高くなるの?
福岡のマンションはいつまで高くなるの?
先月、自宅マンションの「固定資産税」と「都市計画税」を納税した。
家屋の課税標準額は前年と変わらずだが、
土地の「固定資産税」「都市計画税」ともに前年比7%アップしていた。
区役所に確認すると、地価の上昇によるものとのこと。
なるほど、西区(福岡市)の地価も上がっているのか。
3月26日、不動産取引の基準価格といわれる
2024年の「公示地価」(今年1月1日時点の土地の価格)が公表された。
上昇が続いていた福岡県の地価は、
なんと今年も全国トップクラスの上昇率だったらしい。
いったいいつまで高くなるんだろうか。
そこで、少し福岡の地価上昇の状況を調べてみました。
※以下記事は公開情報からデータ引用等を含む。
◎福岡県の地価は今後も上昇が続く見込み
福岡県内では、住宅地、商業地、工業地3つの用途の平均変動率が10年連続で上昇し、上昇率は全国1位!しかも3年連続で上昇幅が大きくなっているそうだ。
用途別の上昇率では「商業地」が4年連続の全国1位、「住宅地」が2位、「工業地」が4位とのこと。福岡市の地価の上昇率、恐るべし!
◎「公示地価」福岡県の住宅地トップは「大濠1丁目」。
福岡県の「住宅地」で価格トップとなったのは、去年と同じく福岡市の「中央区大濠1丁目」。1㎡あたりの価格は114万円、前年より17万円もアップ!福岡市内では再開発や人口増加などを背景に、新築分譲マンションの販売がまだまだ好調で、利便性の高い都市部エリアの物件は実需としても投資物件としても人気が高く、今後も地価の上昇が続くと見込まれているらしい。
◎「公示地価」福岡県の商業地トップは「博多区竹丘町2丁目」。
福岡県の「商業地」で上昇率トップとなったのが、福岡市「博多区竹丘町2丁目」。周辺では、3月16日に西鉄天神大牟田線で14年ぶりの新駅「桜並木駅」が開業。線路が高架化されて周辺道路での渋滞が解消されたこともあり、上昇率は前回より7ポイントも高い21.6%となったそうだ。
◎「公示地価」工業地 上昇率トップは「志免町別府西1丁目」。
福岡県の「工業地」で上昇率トップだったのが「志免町別府西1丁目」。上昇率は20.2%で全国9位にランクイン!福岡市中心部や福岡空港からのアクセスもよく、高速のインターも近い志免町は昨年9月に新たな大型物流施設が竣工するなど、物流の拠点としても需要が高まっているそう。この高い上昇率の背景には、世界的な半導体メーカー「TSMC」の熊本県進出の波及効果もあるのではとのこと。県内の地価が県外から影響を受けるなんて、イマドキなんですね。
◎売れる新築マンション、売れない新築マンションの二極化?
昨今地価上昇が続く福岡県ですが、専門家の間ではマイナス金利政策の解除の影響が出る可能性があるとも指摘されています。
金融緩和などでさらに高騰した土地と値上がりした建築費や工務費などのコストを販売価格に転嫁して一段と物件が高くなるのではとのこと。実際、福岡市内だけでなく、佐賀市や長崎市などでも「億ション」や「タワマン」が発売され、高額な住戸が早々と完売しています。
そんな高額物件でも購入希望者がいるんですね。しかし中には郊外や難しい立地では、なかなか売れない物件が出てくる可能性が高まってくるとも言われています。
◎まとめ
福岡県の地価上昇についてお伝えしてきましたが、
今後の金利政策によっては「売れる物件」と「売れない物件」とに二極化する可能性もありそうです。
予想ですが、そのうち売れないマンションが値引き販売され始めると、
市場全体に影響が出てくるかもしれません。
「うーん、じゃいつマンション買ったらいいの??」となりますが、
実需であれば「買いたいときが買い時」とはよく言われます。
その欲しいと思ったマンションの部屋と全く同じ部屋(階数等)はどこにもありませんので。
不動産エージェントとして個人的な意見ですが、
無理して住宅ローンを組んで新築マンションを狙うより、
中古マンションを探すことも視野に入れてみてはいかがでしょうか。
このところ都市部の中古マンションも高くなっていますので、
今のうちに「身の程」の価格帯で「ちょっと郊外だけど交通利便性の良い中古マンション」を探す、
というのも選択肢の中に入れておいた方がいいかもしれませんね。
関連記事